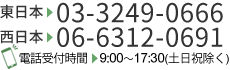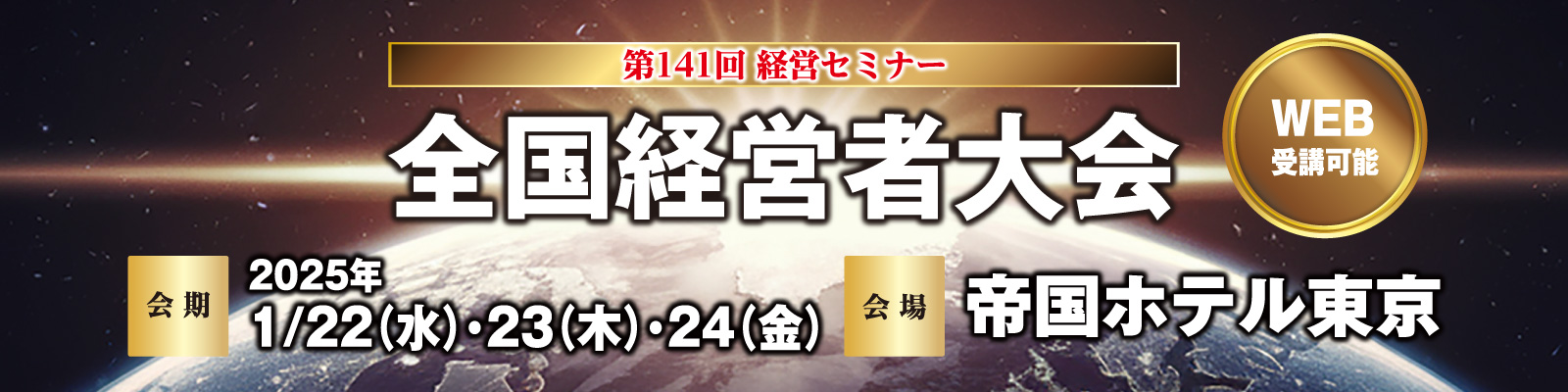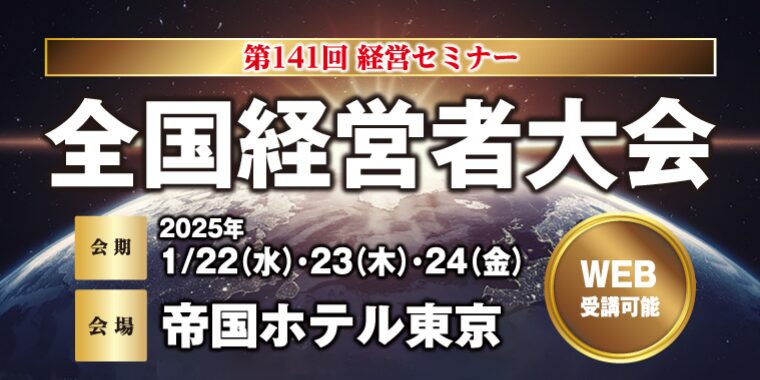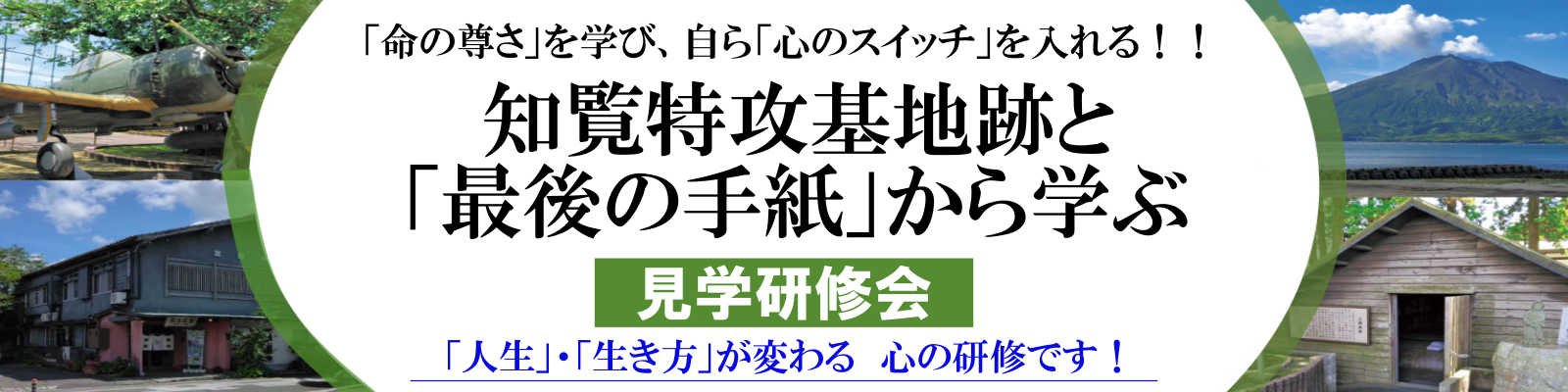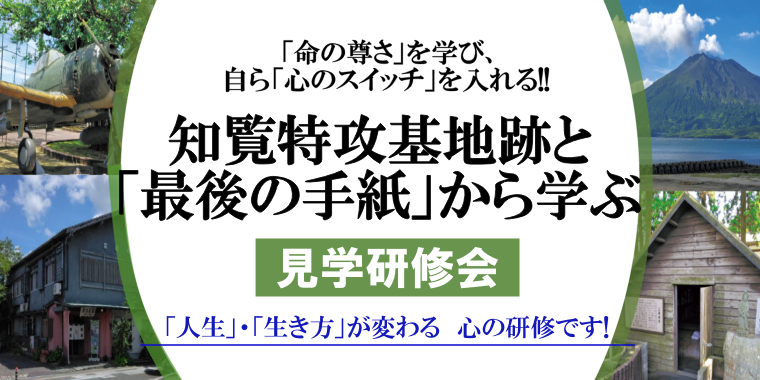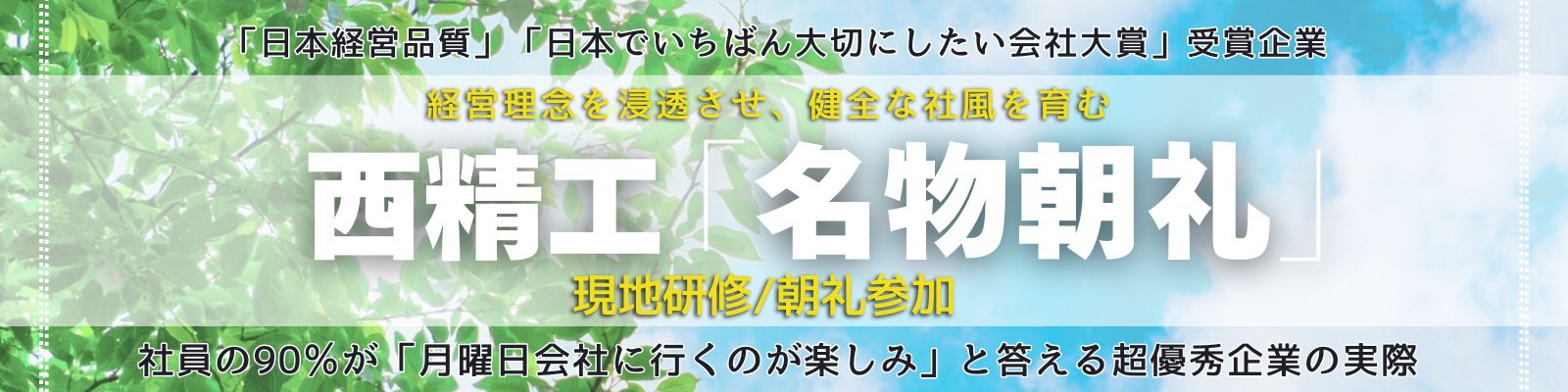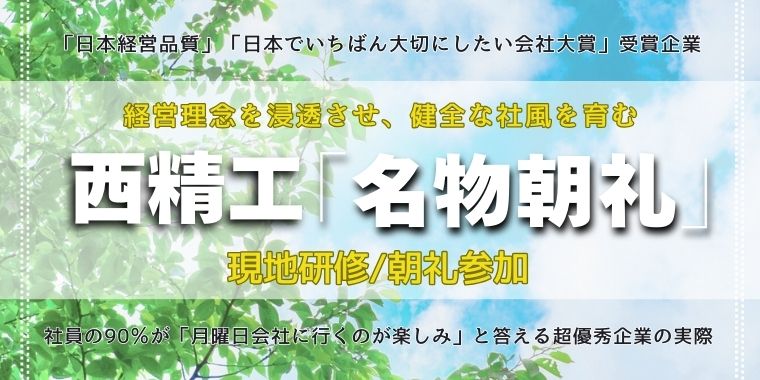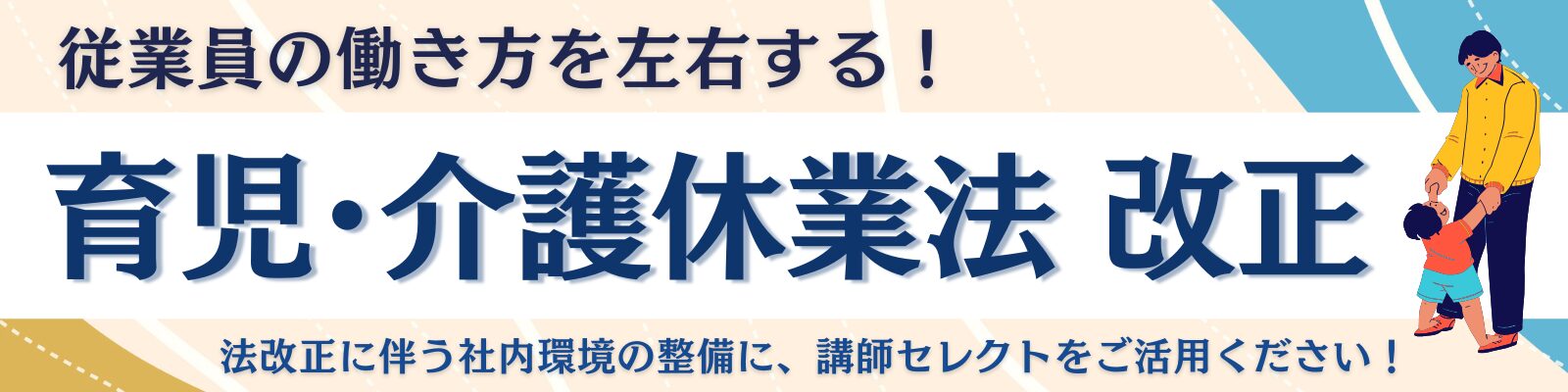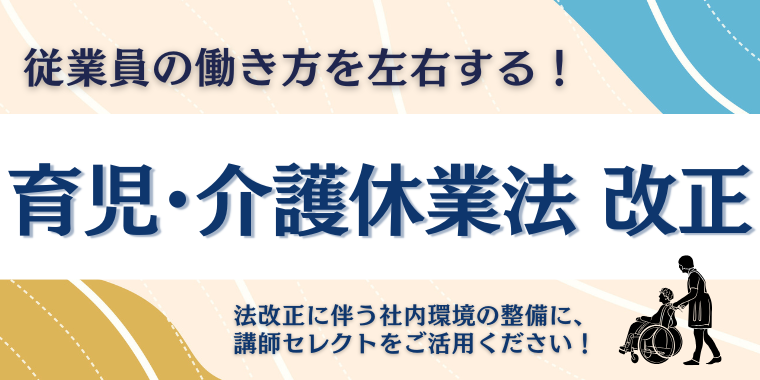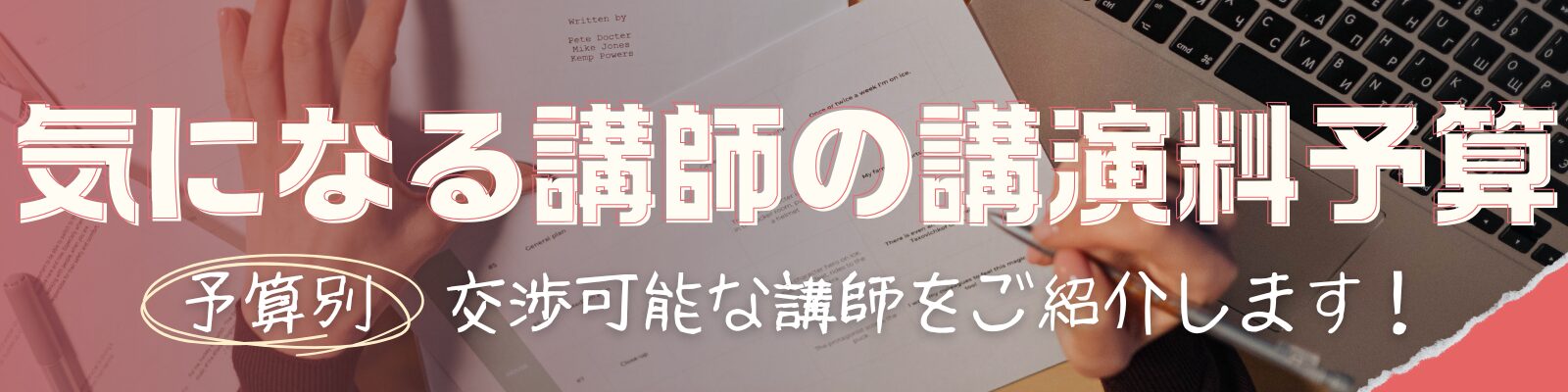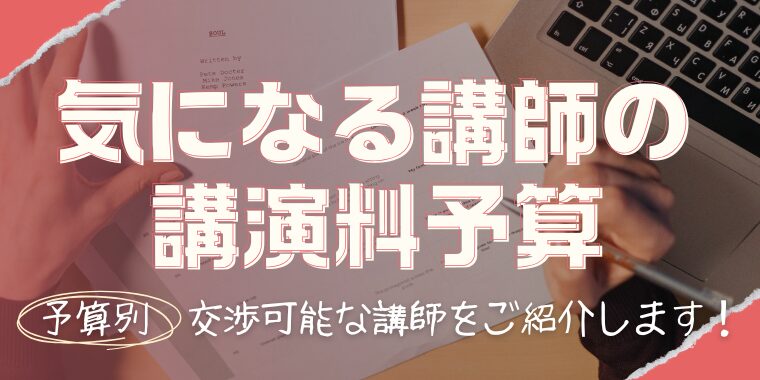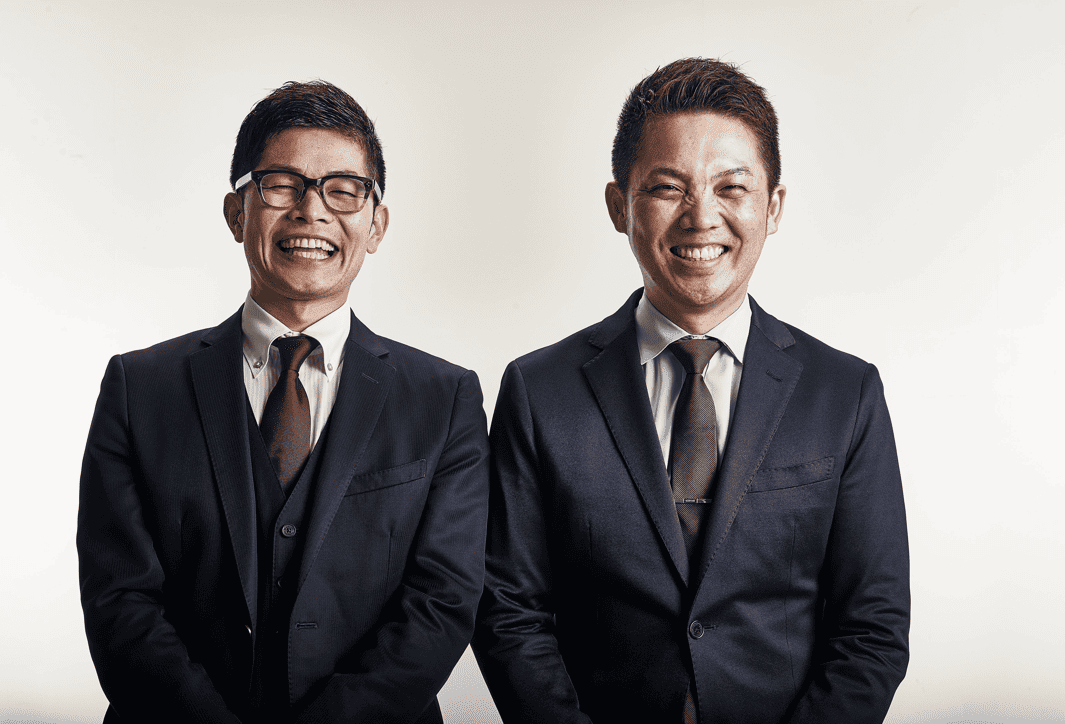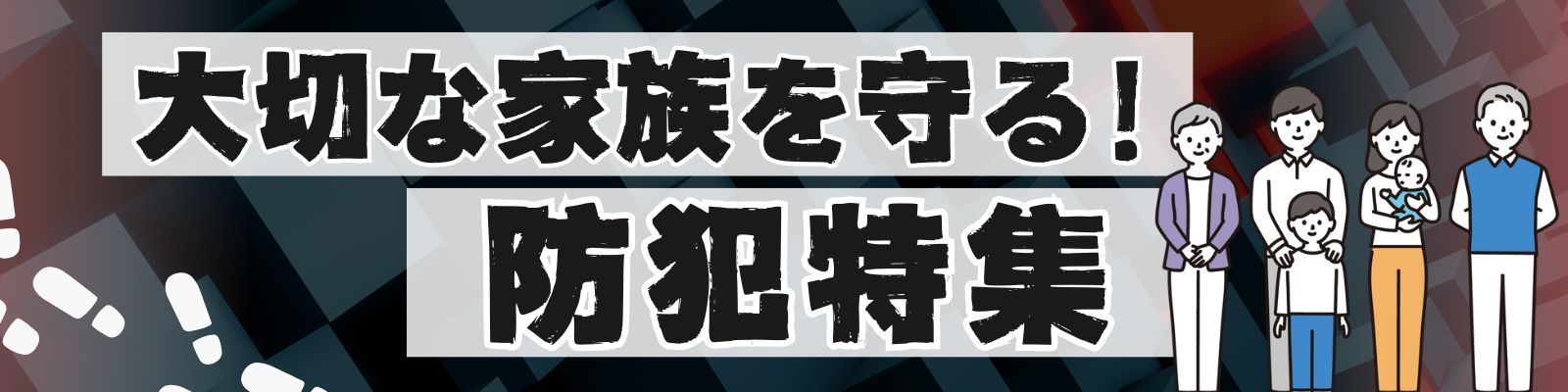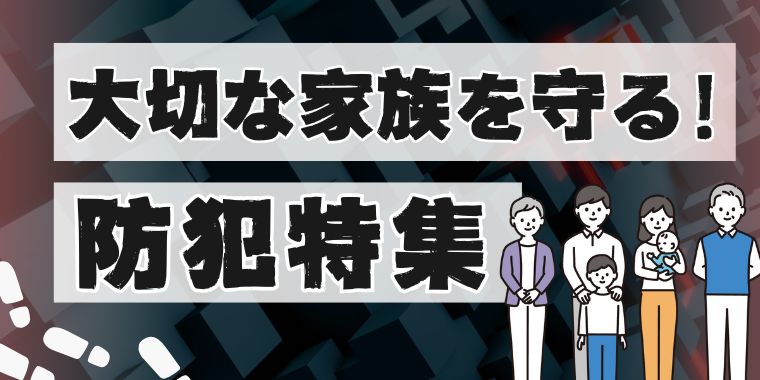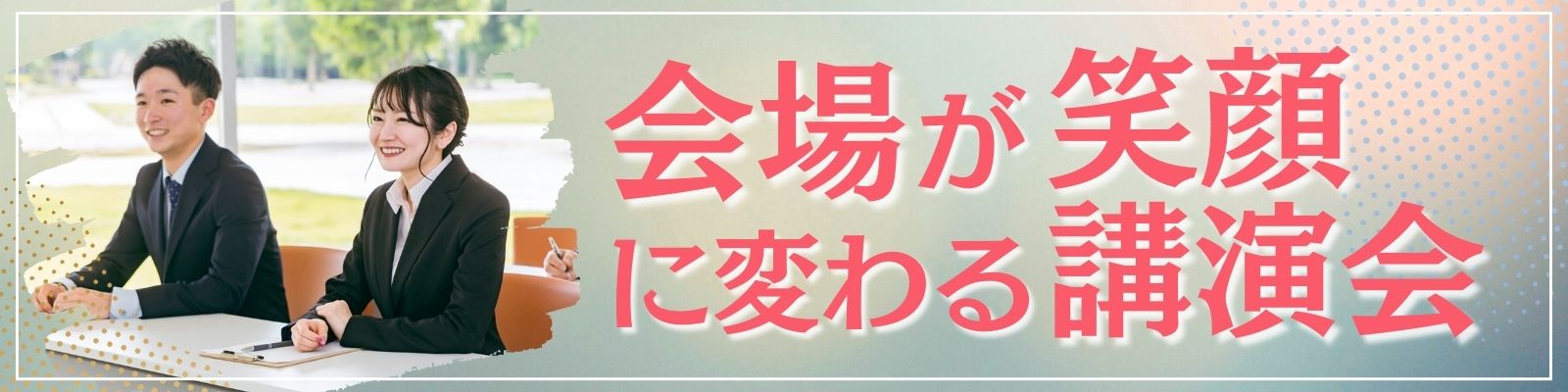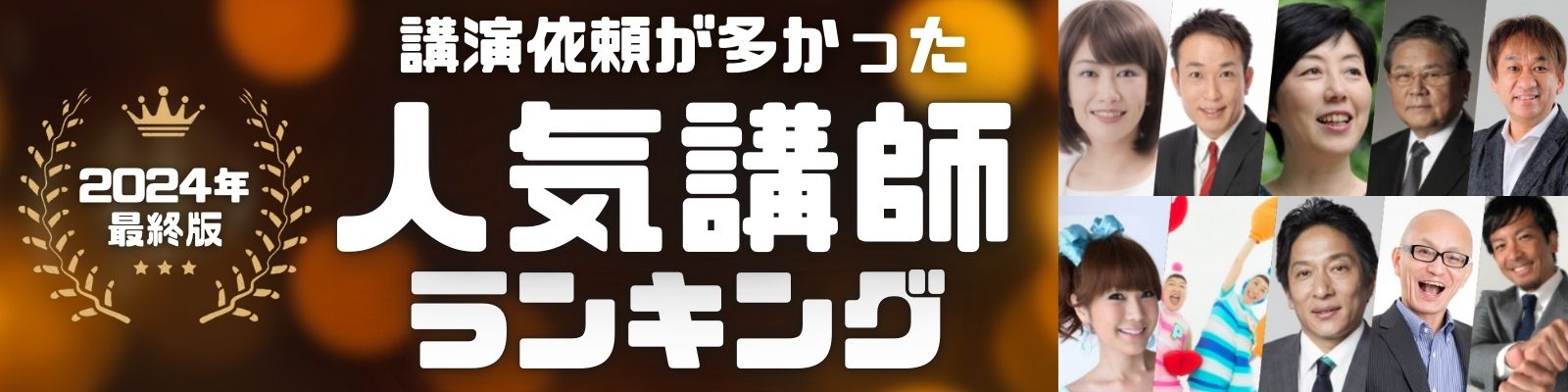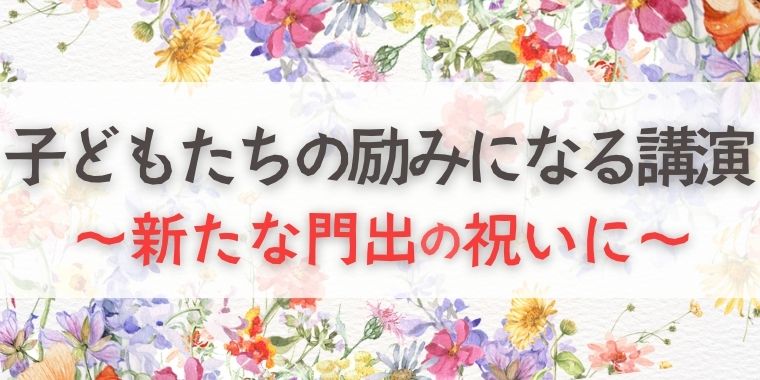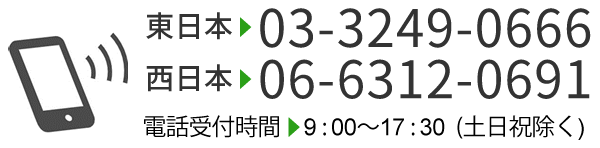寺島 知春

絵本研究家/ワークショッププランナー/著述家
東京学芸大学個人研究員
講師カテゴリー
- 経営・ビジネス
- ダイバーシティ
- ビジネス研修
- 新入社員研修
- 安全大会
- コミュニケーション
- メンタルヘルス
- 健康管理
- セルフマネジメント
- モチベーション
- 夢・希望・挑戦
- 意識改革・気づき
- 人権・福祉・介護
- 平和・国際・異文化
- 子どもの人権
- 学校教育・PTA・育児
- 育児・幼児教育
- 学生向け
- 芸能・エンタメ・芸術
- パフォーマー
- その他芸術
- ライフスタイル
- ライフプラン・自己啓発
出身地・ゆかりの地
福島県 埼玉県 東京都 山梨県 愛知県 滋賀県 イタリア スペイン 中国
この講師について問い合わせる
お急ぎの方はお電話ください
- 東日本
03-3249-0666 03-3249-0666 - 西日本
06-6312-0691 06-6312-0691
プロフィール
1983年名古屋市生まれ。約400冊の絵本を小学校卒業まで毎晩読み聞かせられて育つ。絵本編集者、大手新聞社などの編集者を経て、東京学芸大学大学院で絵本とワークショップの研究を行い、現在に至る。これまでに読んだ絵本は10000冊を超える。
絵本・ワークショップの両専門テーマともに、「遊び」をキーワードとし、生涯発達・美術教育・心理の観点から情報提供している。子どもの視点に立った絵本解説、ワークショップで体感理解を促す講演・講義には定評がある。著書に『非認知能力をはぐくむ絵本ガイド180』(秀和システム)。ワークショップレーベル「アトリエ游」を主催し、全国各地でワークショップ講演を行うほか、雑誌・web連載も。
講演テーマ
【非認知能力と絵本】
●非認知能力と絵本の関係について詳しく取り上げた国内初の著書『非認知能力をはぐくむ絵本ガイド180』の執筆背景や採用絵本の紹介を通して、話題の「非認知能力に絵本がどう関わっていくか」を語る。
●子ども時代に約400冊の絵本を読んだ視点や、元・絵本編集者の視点から、「親子の絵本とのつきあい方」を語る。
●ワークショップ部分で、上記テーマの重要部分を体感理解させる。
【大人と絵本】
●セルフケアとしての絵本の楽しみを、方法、選び方の立場から、絵本の専門家が伝える。
●ワークショップでは、簡単な美術遊びを通して、自己を深く探る。
【子どもへのワークショップ手法】
研究や仕事を通してたくさんの子どもと関わってきた経験や、現在子ども向けのワークショップを多数提供している視点から、「子どものワークショップ」について語る。
●子どもへのワークショップの「構成」、「手法」を語る。
●参加者対象の、子どもへのワークショップ提供体験。
実績
◎講演・ワークショップ
●福島県「アートで広げるみんなの元気プロジェクト2022」ワークショップ(2023)
●彰栄保育福祉専門学校 認定絵本士養成講座 講義(2022ー)
●一般社団法人古河青年会議所 ワークショップ講演(2022)
●一般社団法人能代青年会議所 ワークショップ講演(2022)
●絵本専門店トロル(東京・東村山)ワークショップ(2022)
●JR中央線コミュニティ&東京学芸大学「セレオ国分寺オープンスタジオ」ワークショップ(2021)
●板橋区・板橋区立美術館「ボローニャ絵本さんぽ」ワークショップ(2021-2022)
●山村学園短期大学 子ども学科 ゲスト講義(2019)
●共立女子中学高等学校(高等部) ゲスト講義(2019)
●女子美術大学 芸術学部 メディア表現領域 ゲスト講義(2013ー2018)
◎コラボレーション
●板橋区・板橋区立美術館「ボローニャ絵本さんぽ」協力出展(2021,2022)
●JR中央線コミュニティ&東京学芸大学「セレオ国分寺オープンスタジオ」企画・絵本ディレクション(2021)
◎メディア連載
●雑誌連載「非認知能力を育む絵本」FQKids(2023-)予定
●web連載「子どもの視点でストン!とわかる絵本〜てらしま家の絵本棚から〜」絵本ナビスタイル(2019-2021)
●web連載「e絵本」リセマム(2011-2013)
●web連載「カフェでほっこり絵本時間」ぶらり下北沢(2011-2013)
◎メディア出演
〈雑誌〉
●アクセスインターナショナル「FQKids」2023年1月号
●朝日新聞出版「AERA」2016年9月19日号
〈新聞〉
●福島民報 2023年2月4日付
〈web〉
●FQKids web版 2022年11月21日付より4週連続
●未来へいこーよ 2022年5月30日付
●立川経済新聞 2021年12月21日付
〈TVその他〉
●黒潮町ケーブルテレビ放送 2022年
講演の特徴
子どもたちは絵本を、子どもならではの視点で楽しんでいます。約400冊の絵本を毎晩読んで育ったからこそわかる「子ども視点」をお伝えしながら、絵本の本当の楽しみや、非認知能力・生涯発達といった将来への視点まで展開する講座です。ワークショップ部分では、絵本の面白さを実際に体感していただけます。
著書
『非認知能力をはぐくむ絵本ガイド180』寺島知春、秀和システム
動画
youtubeチャンネル動画(某テレビ番組タイアップ企画)近日公開予定
この講師について問い合わせる
お急ぎの方はお電話ください
- 東日本
03-3249-0666 03-3249-0666 - 西日本
06-6312-0691 06-6312-0691
同じカテゴリーの講師一覧
- 山内 康義就活支援コーチ 人材育成トレーナー▶【たくましく育てよう 優良企業に入社して活躍できる人材になるまで】講師候補に入れる
- 八田 幸子一般社団法人日本声ヨガ協会 代表理事 健康経営アドバイザー マインドフルネス瞑想講師▶【パフォーマンス向上のための睡眠改善】講師候補に入れる
- 山口 幸文千葉商科大学大学院客員教授 (日本中小企業学会会員、日本工芸学会会員) 一般社団法人日本スポーツ・ヘルスケア・デザイン推進機構 理事 一般社団法人次世代構内光ネットワーク整備機構 代表理事▶【アフターコロナを見据えての経営戦略】講師候補に入れる
- 大場 弘枝株式会社なごみ 代表取締役 接客コンテスト全国大会優勝(ファストフード) サービス接遇検定1級 人材開発コンサルタント 集客・CSコンサルタント 農山漁村発イノベーションサポートセンター専門家登録(中央・静岡・愛知) ▶【現場がイキイキと働くスタッフマネジメント】講師候補に入れる
- 岩見 奈津代meeet 言語化プロデューサー 2030SDGsゲームファシリテーター 元女性雑誌編集長 ワークショップデザイナー▶【SDGs研修《各種対応》】講師候補に入れる
- ダイアン吉日バイリンガル落語家、バルーンアーティスト ▶【ダイアンから見た日本 ~笑いで世界をひとつに~】講師候補に入れる
いま注目の講演会講師一覧
- 原 邦雄一般財団法人ほめ育財団 代表理事 株式会社スパイラルアップ 代表取締役/ほめ育コンサルタント▶【ハラスメント防止、中小企業の最大リスクの一つ、労使関係が一気に改善する「ほめ育」420社以上に導入 『部下とのコミュニケーションが一気に改善 “ほめ育”コミュニケーションセミナー』】講師候補に入れる
- 廣田 さえ子 SAEKO HIROTA株式会社デルタマーケティング エグゼクティブプランナー (リクルートトップパートナー代理店所属)▶【リクルート営業9期連続NO.1営業が語る 商談の秘訣】講師候補に入れる
- 伊藤 和人日本経営開発協会 JMDA教育研修センター室長 人材育成コンサルタント▶【職場の多様性を尊重するコミュニケーション】講師候補に入れる
- WマコトCLASSIX株式会社 代表取締役 放送作家(元・吉本芸人) お笑い研修プログラム講師▶【バラエティ現場から学ぶ!『笑撃ビジネスコミュニケーション術』】講師候補に入れる
- 仲内 真弓一般社団法人医療接遇ホスピタリティ協会 代表理事 ▶【WEB セミナー 「今日から実践!アフターコロナ時代の医療接遇」】講師候補に入れる
- 中路 和宏組織改革研究所代表 万松青果株式会社代表取締役会長 中小企業診断士 一級販売士▶【中小企業「わかもの」採用戦略ーブルーカラー編「主人を面接に行かせてもよろしいですか?」】講師候補に入れる
月間講師依頼ランキング
先月の講演依頼のお問合せが多い講師をランキング形式でご紹介
- 1位新井 紀子国立情報学研究所社会共有知研究センター センター長・教授 総合研究大学院大学複合科学研究科情報学専攻教授 国立情報学研究所情報社会相関研究系教授 一般社団法人 教育のための科学研究所 代表理事・所長
▶【わが国の経済成長に向けてAIが果たす役割】講師候補に入れる - 2位
- 3位
講演会の講師派遣レポート
- 2025年03月11日 日本製鉄 橋本会長のご講演―超大企業トップの“腹の据わった不退転の覚悟”を受け取りました!(今春 全国経営者大会講演への感想として①-2【後編】)
- 2025年03月11日 日本製鉄 橋本会長のご講演―超大企業トップの“腹の据わった不退転の覚悟”を受け取りました!(今春 全国経営者大会講演への感想として①-1【前編】)
- 2025年02月19日 <講師派遣レポート> 村瀬健氏 講演会『好かれて、信用されて 買っていただく コミュニケーション術』
- 2025年01月28日 <講師派遣レポート>山口泰信氏講演会『大災害から人命を守り事業を継続させるために~被災経験から語る企業必須の「防災BCP」~』
- 2024年11月29日 <講師派遣レポート>中野信子氏講演会『AIと人間社会の協創社会に向けて』