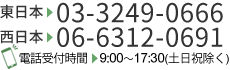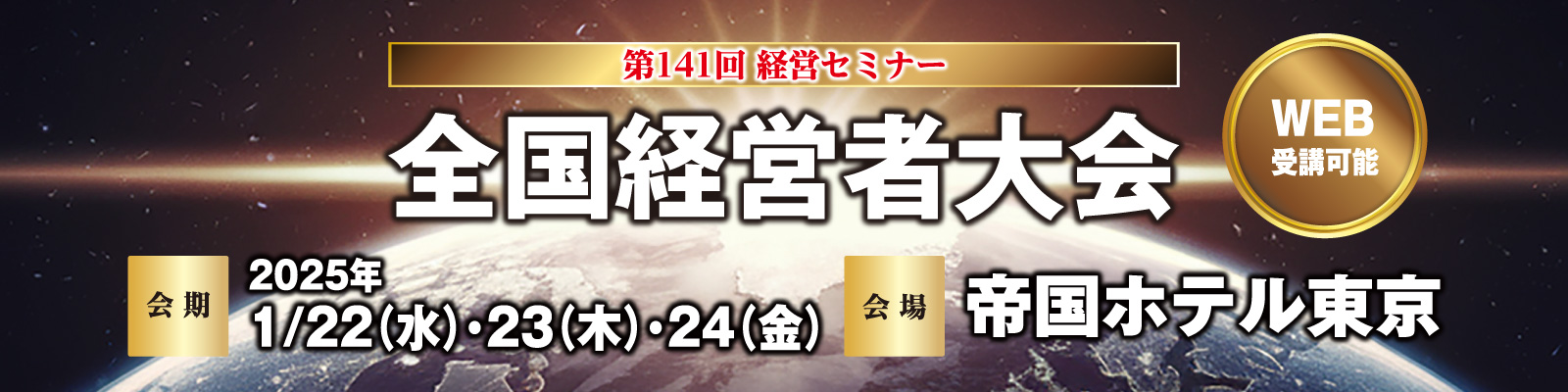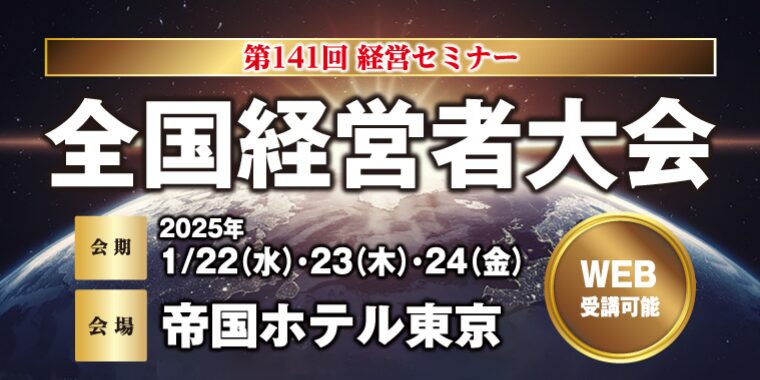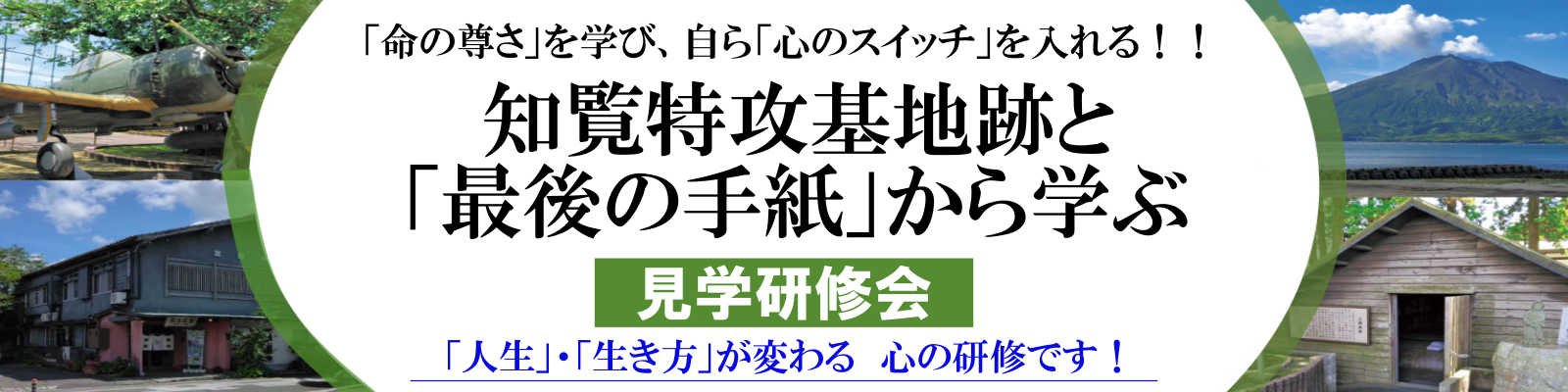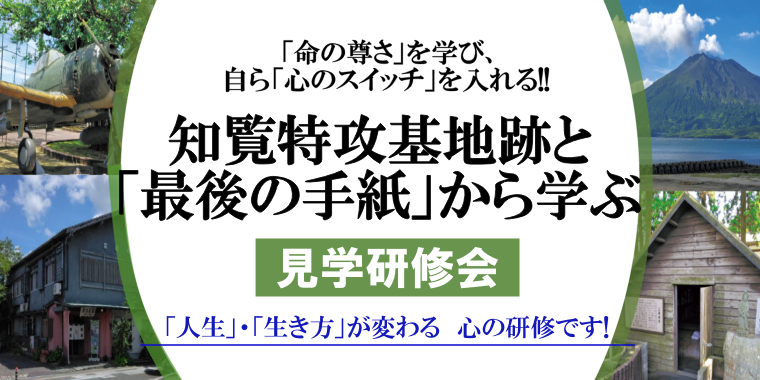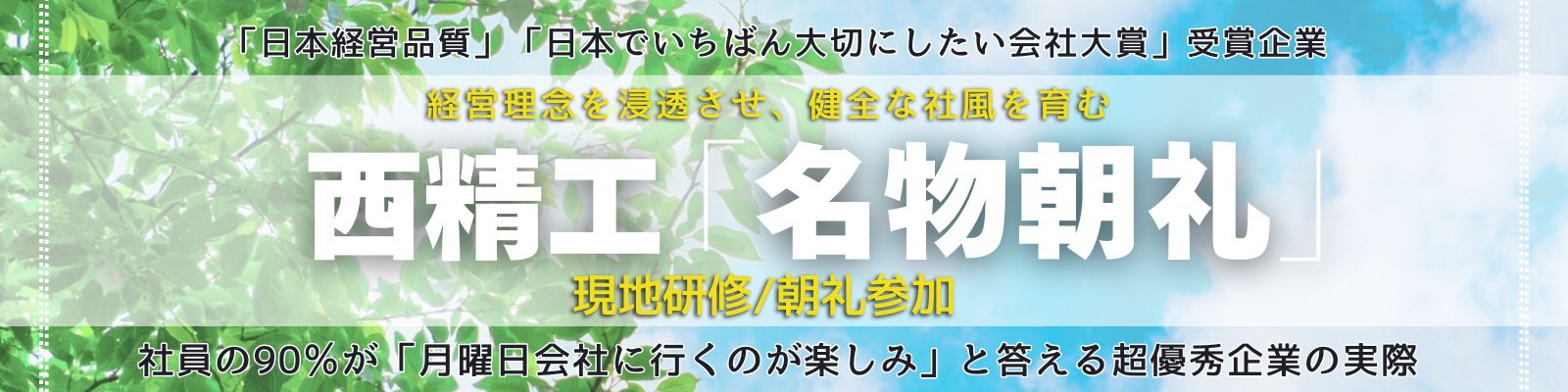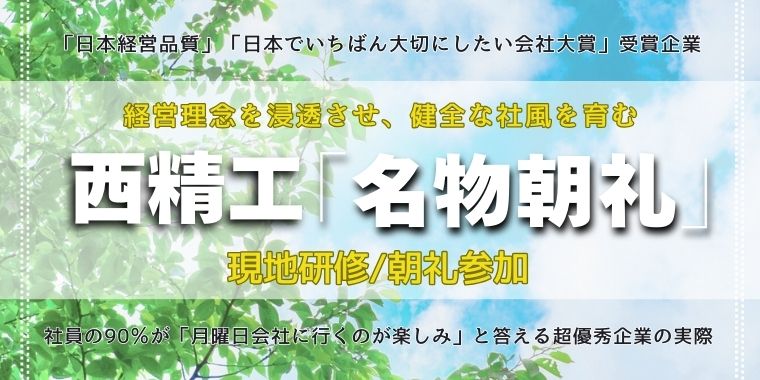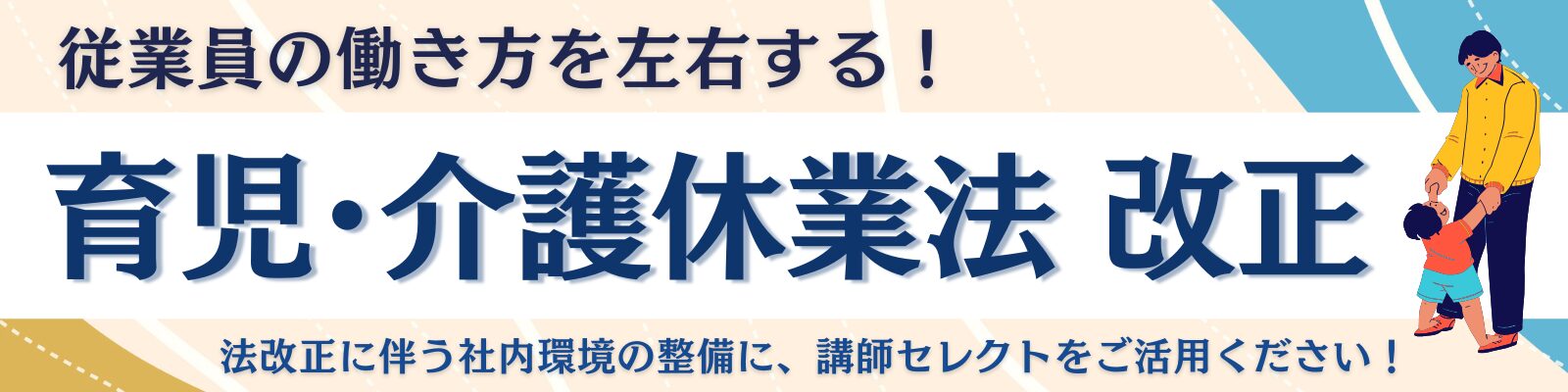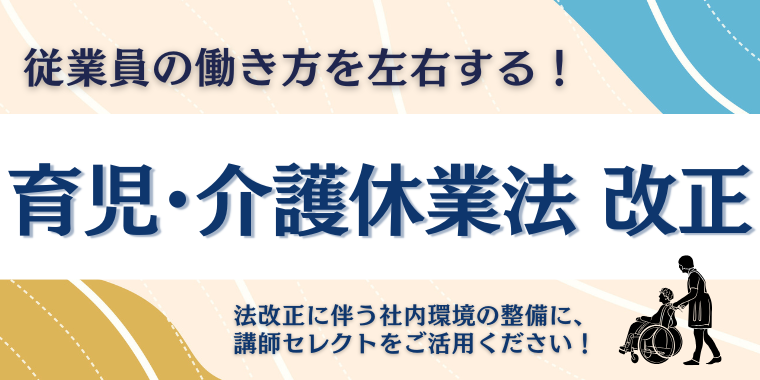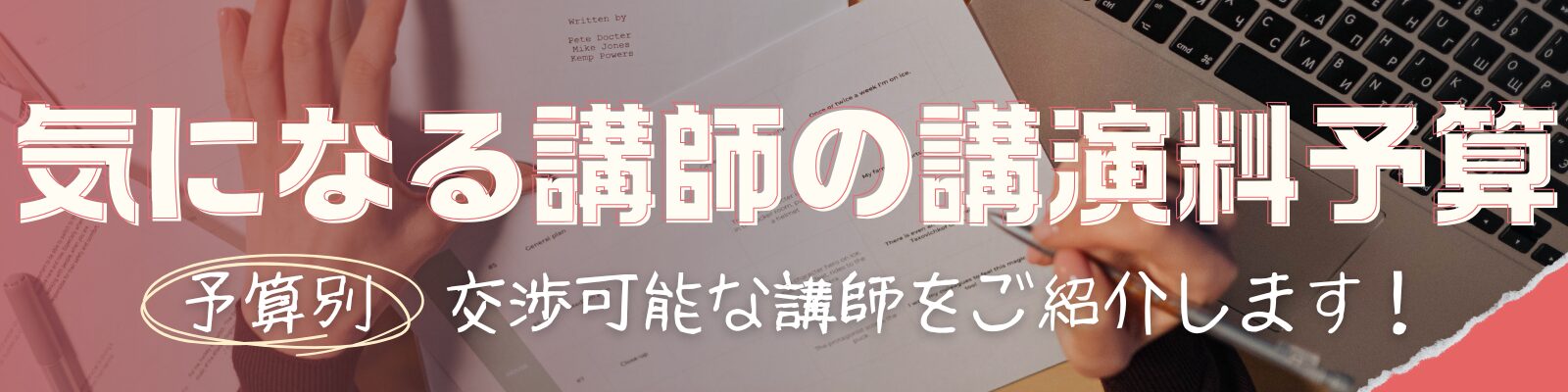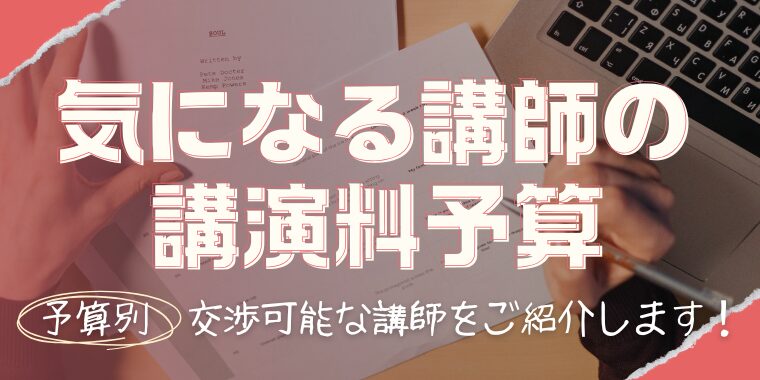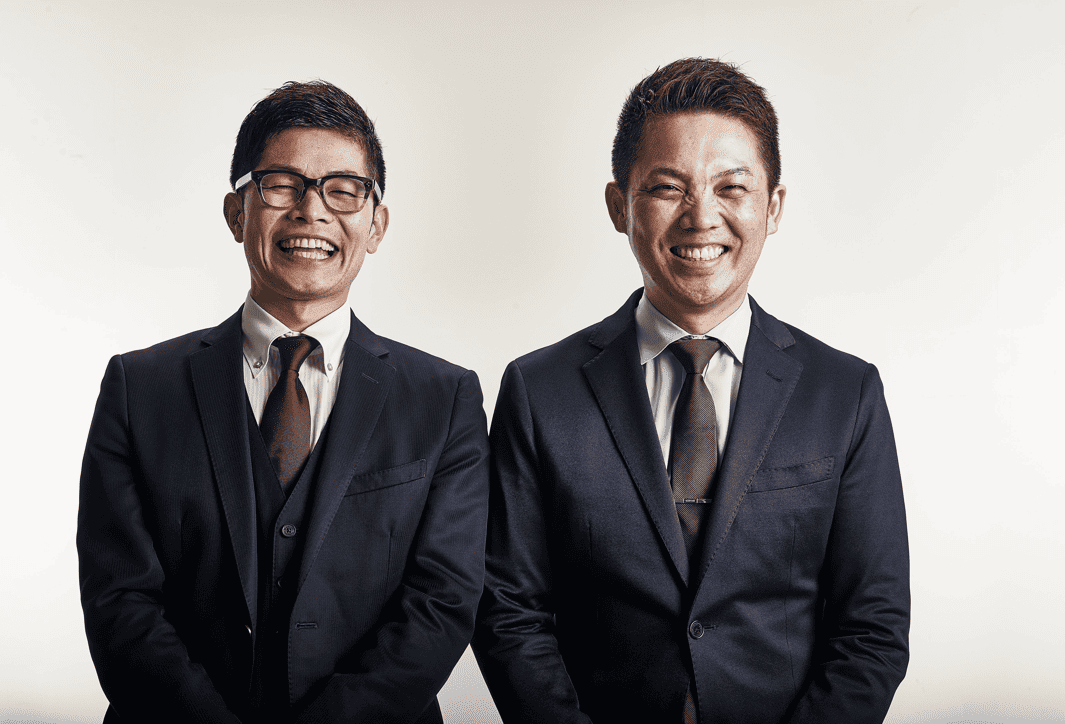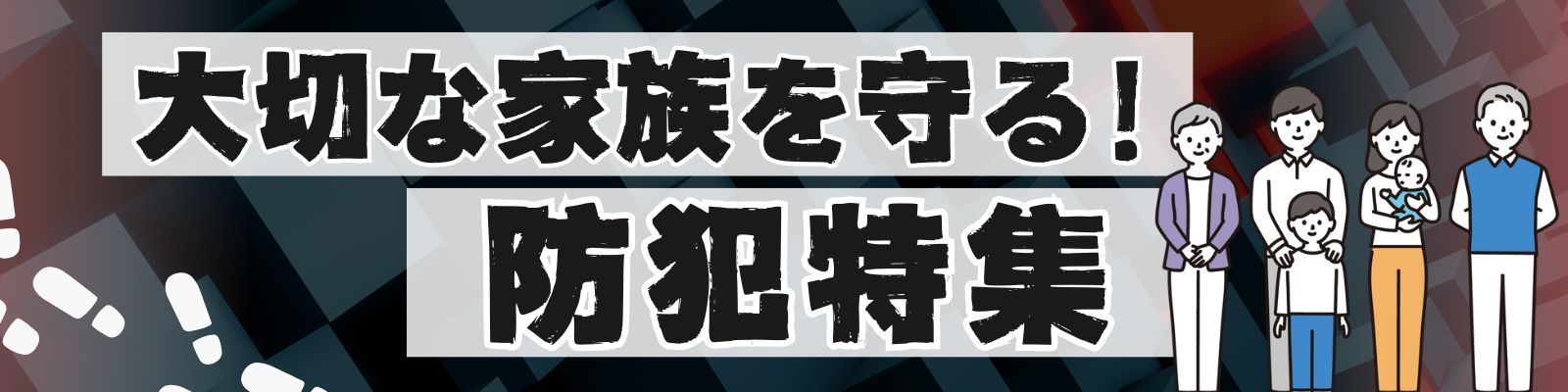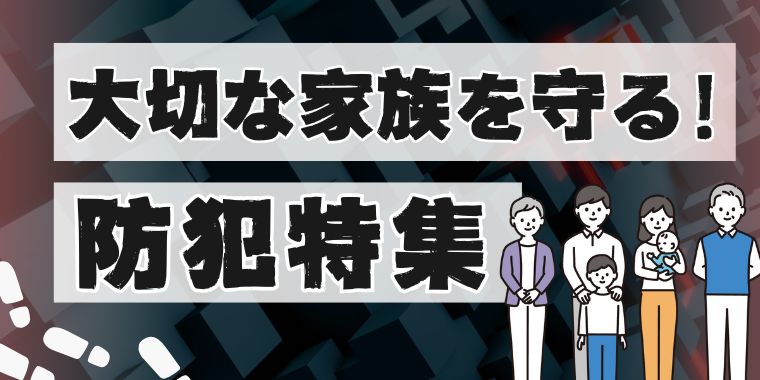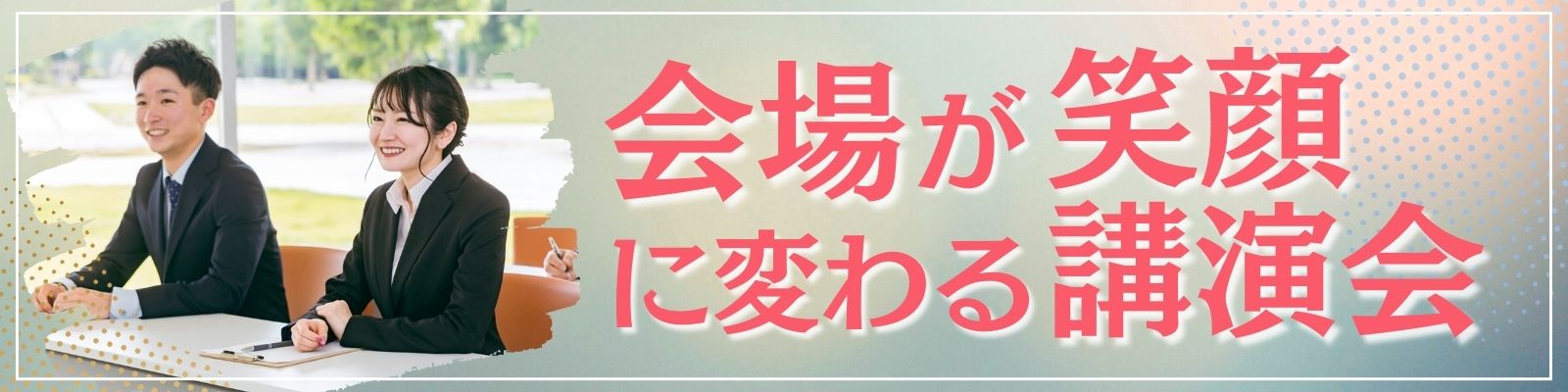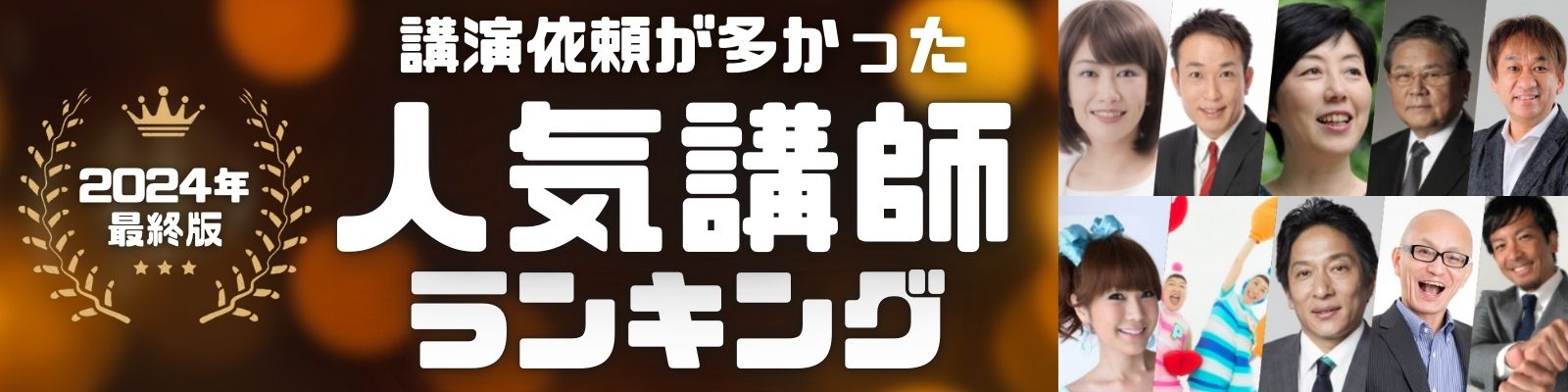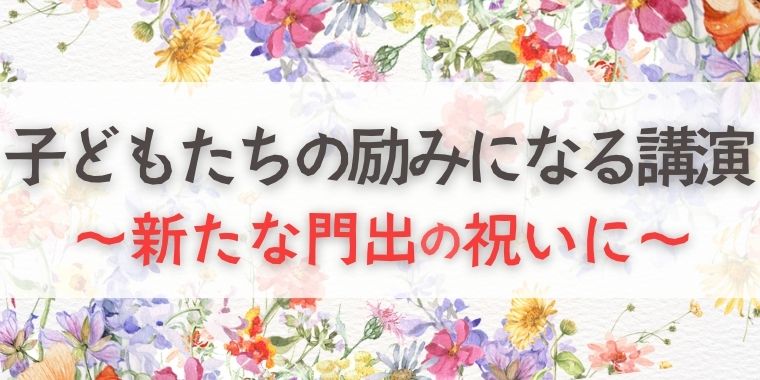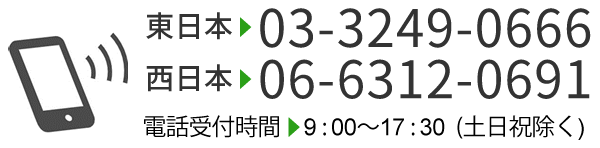竹下 貴文

採用LABO 代表
人事・採用コンサルタント
講師カテゴリー
- 経営・ビジネス
- 人事・採用
- ダイバーシティ
- ビジネス研修
- リーダーシップ・マネジメント
- コミュニケーション・世代間ギャップ
- ビジネスマナー
- 新入社員研修
- モチベーション
- 夢・希望・挑戦
- 人権・福祉・介護
- 障がい・発達障害
- スポーツ
- オリンピック・パラリンピック
- その他スポーツ
出身地・ゆかりの地
岐阜県 愛知県
この講師について問い合わせる
お急ぎの方はお電話ください
- 東日本
03-3249-0666 03-3249-0666 - 西日本
06-6312-0691 06-6312-0691
プロフィール
【略歴】
1972年4月 愛知県生まれ
1996年6月 愛知県内 私立大学卒業(経済学)
1996年3月 大手学習塾に講師として入社
1997年7月 上場出版社に営業として転職
2000年4月 同社にて人事へ異動
2004年2月 上場技術派遣会社へ人事として転職
2011年1月 ビルメンテナンス会社へ人事として転職
2014年4月 技術者派遣会社へ人事として転職
2017年1月 採用LABO開業
プロトコーポレーション(情報出版)、日本テクシード(技術者派遣/現 パーソルR&D)、ホーメックス(清掃・廃棄物処理・公共建物管理)、ディーピーティー(技術者派遣)にて採用、教育、制度構築を経験。
ホーメックスを除いた3社は大量採用企業であったため、トータル1万人の面接経験あり。
教育、制度構築に関しても在籍4社ともアウトソーシングする文化がなかったため、人事担当として内製。
在籍4社全てで管理職を経験しているため組織運営や経営課題への対応も最前線にて行ってきた実績あり。
戦略立案、説明会運営、面接などに豊富な成功例を持つ。
講演テーマ
【面接経験1万人!今も面接依頼が舞い込み続ける「面接のプロ」が面接の奥深さ、重要さ、面接官心得について伝授します】
採用の場面で面接を実施しない企業は皆無です。
しかしながら、面接を実施する面接官は「面接の仕方」を誰かに聞いたり、学んだりする機会がほぼないまま面接官になっている実態があります。
『欲しい人材が採れない』『面接後の歩留まりが悪い』など、実は採用活動の良し悪し左右しているのは面接であることがほとんどです。
”我流面接”を卒業して「原理原則」に基づいた「ミスマッチの起こらない面接」を基本から丁寧に「応募者目線」も交えてお話いたします。
【『カネのかかる採用』からの脱却】
企業活動の中で「採用活動」ほど、企業価値観が分かれる費用はありません。
例えば1億円を掛けて採れるだけ採る採用をする企業もあれば、ハローワークでせっせと求人票を提出する採用活動を行う企業もあります。
しかしその中には『無駄』であったり、『無理』であったり、目に見えない訳の分からないファクターが年々増加傾向にあります。
ダイレクトリクルーティング、スカウト、リファーラル・・多種多様な採用手法から自社にマッチする戦略・戦術はいったい何なのか?本当に採用はカネがかかるのか?
一般論だけでなく、実例を交えながら採用活動にかかるカネの有益な使い方を伝授します。
【採用活動はエースの仕事であり、社員育成の場】
多種多様な企業価値観の中で「採用活動」の重要度はいかほどでしょう?
間違いなく言えることは”バックオフィス担当が片手間で行っているような企業に採用成功はない”ということです。
「人事は自社の代弁者」とは古くから言われてきましたが、採用フローが複雑化、複線化する現在では人事が頑張っただけでは良い採用活動はできにくくなっています。
『うちの会社』を語れる人材を何人も生み出すことによって会社で全体を活性化し、採用活動を育成の場として活用するイノベーションをご紹介します。
【パラリンピアンの家族】
女子車イスバスケットボールプレーヤーとして、2004年アテネパラリンピックや2007年世界選手権にて日本代表だった亡き妻。
2020東京パラリンピックにて日本代表の強化指定選手としても出場を夢見ておりましたが、病のため2018年11月に
逝去しました。
注目度が高まる車イスバスケットボールの魅力や競技環境を知っていただくとともに、日本代表選手と暮らす日常生活はどのようなものであったかを明るく楽しくお話しします。
【(身体)障害者雇用は難しくない】
障害者雇用促進法において2.2%の障碍者雇用率制度が導入されましたが、中小企業では手探り状態のまま、あまり積極的には手を出しづらいと思われがちです。
障害者雇用について、障害者側に立った視点で彼らが「どのように就業を考え、雇用主にどのようなことを望むのか」を
ある一例として妻のケースを例にお話しさせていただきます。
(妻の就業経歴)
トヨタカローラ岐阜→日本テクシード(現:パーソルR&D)→ブラザー工業
実績
・企業内研修、講演(管理職向け、実務者向け)
・オープン講演(採用実務者、採用責任者)
・学生合同説明会内 基調講演
など多数ございます。
講演の特徴
★90分程度のオープン講演だけではなく、半日単位のクローズ研修や複数日程でのクローズ研修、長期にわたるコンサルティングも承っています★
対象者の変更や、レベル合わせなどは事前にオーダーいただければ如何様にもカスタマイズすることが可能です。
お気軽にご相談ください!
この講師について問い合わせる
お急ぎの方はお電話ください
- 東日本
03-3249-0666 03-3249-0666 - 西日本
06-6312-0691 06-6312-0691
同じカテゴリーの講師一覧
- 寺下 薫クリエイトキャリア代表 キャリアコンサルタント(国家資格) 元ソフトバンクユニバーシティ認定講師 元Yahoo! JAPAN人材育成責任者▶【お客様第一向上】講師候補に入れる
- 村瀬 健放送作家 漫才作家▶【お笑い芸人に学ぶ! 豊かな人間関係を築くためのコミュニケーション術】講師候補に入れる
- 植村 真樹R&D戦略・組織活性化アドバイザー 化粧品開発アドバイザー 日本化粧品技術者会 東日本支部事務局長 元株式会社資生堂 フロンティアサイエンス事業部長 社団法人企業研究会 R&Dマネジメント交流会議 副コーディネーター 、同開発塾 コーディネーター▶【”つなぐ”リーダーシップで変革をリードし、組織を元気にする】講師候補に入れる
- 高島 徹株式会社決断力 代表▶【TOP企業研修「企業が直面している課題と、弊社のお役立ち」】講師候補に入れる
- 萩原 京二株式会社 全就連 代表取締役(社会保険労務士) 一般社団法人 ディーセントワーク推進協議会 代表理事 特定非営利活動法人 労働契約エージェント協会 理事長▶【中小企業のSDGsへの取り組み】講師候補に入れる
- 鬼本 昌樹戦略人財コンサルタント▶【視点の流動化】講師候補に入れる
いま注目の講演会講師一覧
- 原 邦雄一般財団法人ほめ育財団 代表理事 株式会社スパイラルアップ 代表取締役/ほめ育コンサルタント▶【ハラスメント防止、中小企業の最大リスクの一つ、労使関係が一気に改善する「ほめ育」420社以上に導入 『部下とのコミュニケーションが一気に改善 “ほめ育”コミュニケーションセミナー』】講師候補に入れる
- 廣田 さえ子 SAEKO HIROTA株式会社デルタマーケティング エグゼクティブプランナー (リクルートトップパートナー代理店所属)▶【リクルート営業9期連続NO.1営業が語る 商談の秘訣】講師候補に入れる
- 伊藤 和人日本経営開発協会 JMDA教育研修センター室長 人材育成コンサルタント▶【職場の多様性を尊重するコミュニケーション】講師候補に入れる
- WマコトCLASSIX株式会社 代表取締役 放送作家(元・吉本芸人) お笑い研修プログラム講師▶【バラエティ現場から学ぶ!『笑撃ビジネスコミュニケーション術』】講師候補に入れる
- 仲内 真弓一般社団法人医療接遇ホスピタリティ協会 代表理事 ▶【WEB セミナー 「今日から実践!アフターコロナ時代の医療接遇」】講師候補に入れる
- 中路 和宏組織改革研究所代表 万松青果株式会社代表取締役会長 中小企業診断士 一級販売士▶【中小企業「わかもの」採用戦略ーブルーカラー編「主人を面接に行かせてもよろしいですか?」】講師候補に入れる
月間講師依頼ランキング
先月の講演依頼のお問合せが多い講師をランキング形式でご紹介
- 1位新井 紀子国立情報学研究所社会共有知研究センター センター長・教授 総合研究大学院大学複合科学研究科情報学専攻教授 国立情報学研究所情報社会相関研究系教授 一般社団法人 教育のための科学研究所 代表理事・所長
▶【わが国の経済成長に向けてAIが果たす役割】講師候補に入れる - 2位
- 3位
講演会の講師派遣レポート
- 2025年03月11日 日本製鉄 橋本会長のご講演―超大企業トップの“腹の据わった不退転の覚悟”を受け取りました!(今春 全国経営者大会講演への感想として①-2【後編】)
- 2025年03月11日 日本製鉄 橋本会長のご講演―超大企業トップの“腹の据わった不退転の覚悟”を受け取りました!(今春 全国経営者大会講演への感想として①-1【前編】)
- 2025年02月19日 <講師派遣レポート> 村瀬健氏 講演会『好かれて、信用されて 買っていただく コミュニケーション術』
- 2025年01月28日 <講師派遣レポート>山口泰信氏講演会『大災害から人命を守り事業を継続させるために~被災経験から語る企業必須の「防災BCP」~』
- 2024年11月29日 <講師派遣レポート>中野信子氏講演会『AIと人間社会の協創社会に向けて』